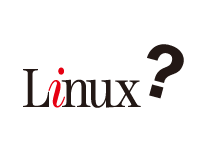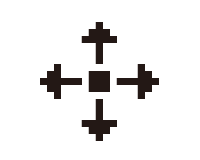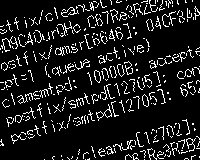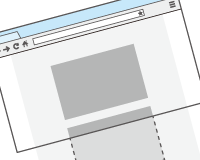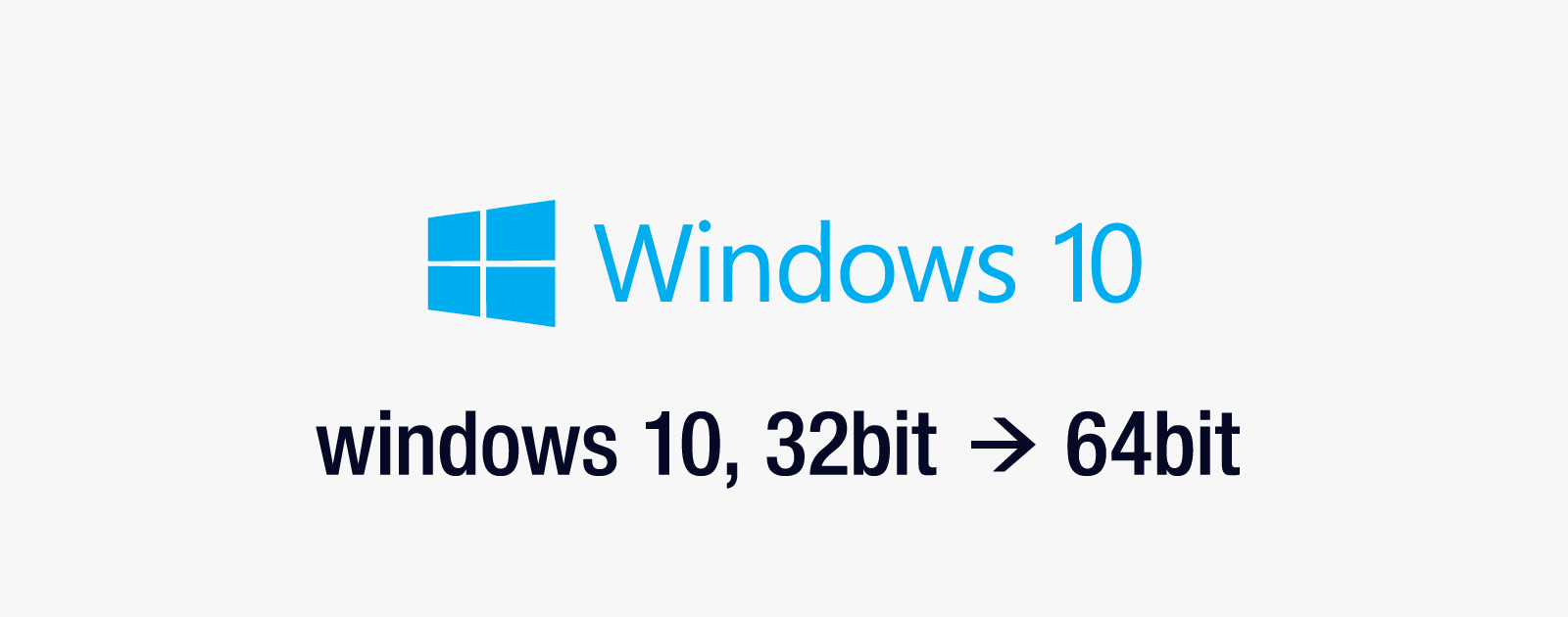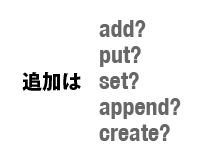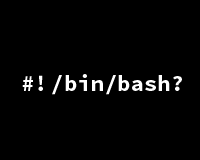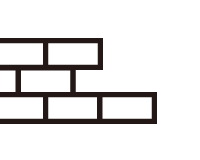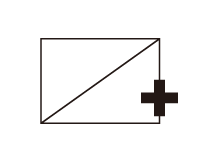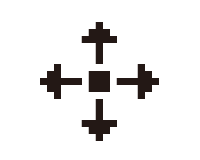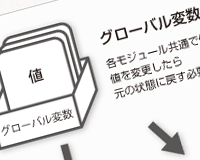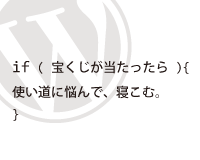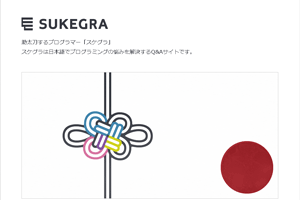愛がなければ、すべてはただの安物芝居にすぎない
社会現象にまでなった本作、気になっていたものの、あえて手には取りませんでした。
「右へ倣え右は嫌い」「オリコン1位は信用しない主義」といった、とても個人的な理由からです。
ところが先日、同じく村上春樹の「ダンス・ダンス・ダンス」を読んだことに刺激されて、遅ればせながら読み始めることになりました。「そろそろほとぼりも冷めた頃だろう」という変な理屈で自分を納得させて。
1Q84は作中でも紹介される、ジョージ・オーウェルの「1984年」に着想を得ています。ビッグ・ブラザーや、それに類するリトル・ピープルという概念からも明らかです。
1Q84が発刊された当時、村上春樹は「何の先入観も持たずに読んでほしいので、事前に何も告知しない」という販売方法を望んだそうです。私もそれに習って、なんの書評も見ずに読みました。
どのような話かわからないというスパイスは、ハルキストはもちろん、毎年のノーベル文学賞騒ぎで刺激された物見遊山的な読者にも有効だったようです。近年の活字業界には珍しく販売待ちの行列などが報じられ、社会現象になりました。
作中で天吾らが共謀して発刊する「空気さなぎ」も巧妙な仕掛けでヒットします。なんだか、現実とリンクしているようで、奇妙な感覚になります。
この小説は謎解きやミステリーといった体裁のため、物語を理解しづらいという特徴があります。とりあえず話を整理するために、大まかに概要をまとめてみます。
目の見えない山羊の口から出てきたリトル・ピープル。ここから世界が変わります。その世界は1Q84であり、猫の世界とも呼ばれます。
リトル・ピープルが「すみか」だと主張する「空気さなぎ」。
リーダーはリトル・ピープルのことを「大昔から彼らと共に生きてきた。まだ善悪がろくに存在しなかった頃から。人々の意識がまだ未明のものであったころから」と解説します。さらに、その存在を説明をできるものはいないと付記します。
最後までリトル・ピープルについて解説されません。そのため個人的な想像ですが、八百万の神や、神の存在、神聖なもの象徴ではないでしょうか。人はそこから信じたい神を紡ぐ。といったタイプの。
「空気さなぎ」からは少女そっくりのドウタが出ます。元の少女はマザと呼ばれます。これはMOTHER(母)とDaughter(娘)のことでしょう。
ドウタはパシヴァの役をする。パシヴァは「知覚するもの」。それを受けるのがレシヴァである「声を聴くもの」。これはパッシブ(受信者、passive、passiver?)と、レシーバー(送信者、receiver)の関係です。
パシヴァはふかえり(深田絵里子)のドウタ。レシヴァはその父、安田保が担う。安田保はレシヴァとなることで、リーダーであり、教祖であり、特別な存在になる。
1Q84の世界で教団となったあけぼのでは10歳になる少女たちが次々とパシヴァとなる。教団ではそれを巫女と呼ぶ。巫女はレシヴァとなったリーダーと「多義的に」交わる。
なぜか巫女たちは妊娠を望む。しかし10歳の彼女達ドウタは生理がなく、生殖能力はない。別の言葉で言い換えると子宮が破壊されている。
そうした世界を、天吾、青豆という二人の登場人物の視点から交互に紡ぐようにストーリーが進められる。物語のテイストは社会問題を扱うドキュメンタリーのようであり、不思議の国のアリスのような童話にもなる。
ドキュメンタリーの部分は村上春樹がかつて取材したオウム事件の知見が数多く登場している。そのため、一見すると現実離れしたストーリーも現代日本人にとってはどこか現実感を持つ。
また、「1984年」のエッセンスは学生闘争に明け暮れる革命派のあけぼのとして登場。
不思議の国のアリスはエッソのタイガーの看板などに現れている。(「エッソ 看板」で画像検索すると顔の右側をこちらに向けて「PUT A TIGER IN YOUR TANK」と書かれた看板が見つかる。中には不思議の国のアリスの中で象徴的な役割を持つうさぎとカメが追加されたバージョンもある)
作中に度々出てくるヤナーチェクのシンフォニエッタはwikiの解説から。(読書後にYoutubeで初めて聴きました)
勝利を目指して戦う現代の自由人の、精神的な美や歓喜、勇気や決意といったもの wikipediaより
まさしくこの作品の主旋律としてふさわしい。
それは過去に重大な問題を抱え、1Q84に迷い込み、生きる意味を勝ち取るストーリーとピッタリと重なります。(軍隊の行進曲としては少々情緒的でありすぎる気がしますが…)
個人的な好みを言わせてもらえば、読書中はシンフォニエッタよりも、アンダーワールドの曲が似合う気がします。
本作では、こうした裏にあるテーマや隠喩をいつもの作品以上に説明していません。
村上春樹の作品を読んだことのある方にとっては、音楽は特別な意味を持ち、少女は不思議な力を持ち、森は精神世界を表し、山羊は生死を司るもの、ということは説明が無くても想像できます。
ただ、初めて村上春樹の作品に触れた人は、だた冗長で同じことを繰り返す、退屈な作品に映るかもしれません。想像を越えるようなどんでん返しも無ければ、手に汗握るサスペンスもありません。特に、度重なるセックスの描写は病的で不快この上ない。
ハルキストたちの中で「続編が出るのではないか」とささやかれるほど、伏線を回収していません。商品のコピーではあるまいし、全ての伏線に回収が必要だとは思いませんが、あまりに投げっぱなしの部分が多く、頭を悩ませます(不思議の国のアリスのように)。
ただ、最後まで読めば、そうした伏線は、あくまで伏線であり、主題とは関係のないことだということが理解できます。トランプの兵隊や、開かない扉のように、読者を楽しませ物語に引き込むギミックにすぎない。むしろ回収しないからこそ、それは伏線であると主張しているかのようです。
ただ、悪いことに、ただでさえ明確でないストーリーが、青豆と天吾という二人の主人公によって細切れに語られることで、さらに迂遠なものになっています。
繰り返されることと、病的であることは、作中の重要なテーマです。しかしそれを考慮したとしても、読み進めるのに骨が折れました。
作者は読者が持つであろう、こうした注文に対して答えています。
作中でヒットする「空気さなぎ」についての書評のなかで以下のようなものがあります。
「我々は最後までミステリアスな疑問符のプールの中に取り残されたままになる。…」
それを受けて天吾が答えます。
「『物語としては面白くできているし、最後までグイグイと読者を牽引していく』ことに作家がもし成功しているとしたら、その作家は怠慢と呼ぶことは誰にもできないのではないか」
これが作者の本音なのだと思います。
と、いじわるな解釈はこれくらいにして、全体を俯瞰して読めば、戦争やイデオロギー闘争。はたまた政治・宗教・社会制度といったあらゆる暴力の中で、取り残された部分。理想や理念が形骸化し、虐げられてきた、狭間の子どもたち。疑問を持ち、迷いながら、それでも受け入れるしか無かった「役割」の生んだ子ども。そうした弱いものに寄り添った物語と言えます。
彼らはリトル・ピープルの持たない真実を獲得して生還する。役割に徹し、心を殺すことで生きながらえていた彼らにとって、精神世界に足を踏み入れることは大きな賭けだったのではないでしょうか。
1Q84から生還するのに必要なもの。不思議な少女ふかえりの言葉を借りれば「だいじなものはもりのなかにありもりにはリトル・ピープルがいる。リトル・ピープルからガイをうけないでいるにはリトル・ピープルのもたないものをみつけなくてはならない」。
つまり作中で何度も語られる「愛」。生の動機となり、死すら恐れないほどの「愛」。もっと言えば「無償の愛」。
「愛がなければ、すべてはただの安物芝居にすぎない」
1Q84から生還して首都高速で天吾と青豆が月を見るシーン。まさしくヤナーチェックのシンフォニエッタがよく似合いそうだ。
最後のホテルのシーンで青豆は元の世界とは異なることに気が付いている。しかし彼女はそんなことは意に介していない。ただ口から「あなたの王国が私達にもたらされますように」と祈る。それは子供の頃に言わされた祈りとは本質的に異なる。
今では文庫本と単行本の2つが出ているみたいですね。
私は単行本を買いましたが、ページのめくりにくい紙で、しょっちゅう2ページまとめてめくってしまい、イライラしました。
今なら文庫本バージョンがオススメです。文庫版は全6巻で、単行本は全3巻です。お間違えのないように。

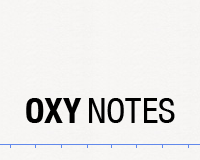 サーバへPukiWikiをインストール
サーバへPukiWikiをインストール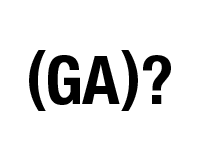 ソフト名に付くGAって何の略?
ソフト名に付くGAって何の略?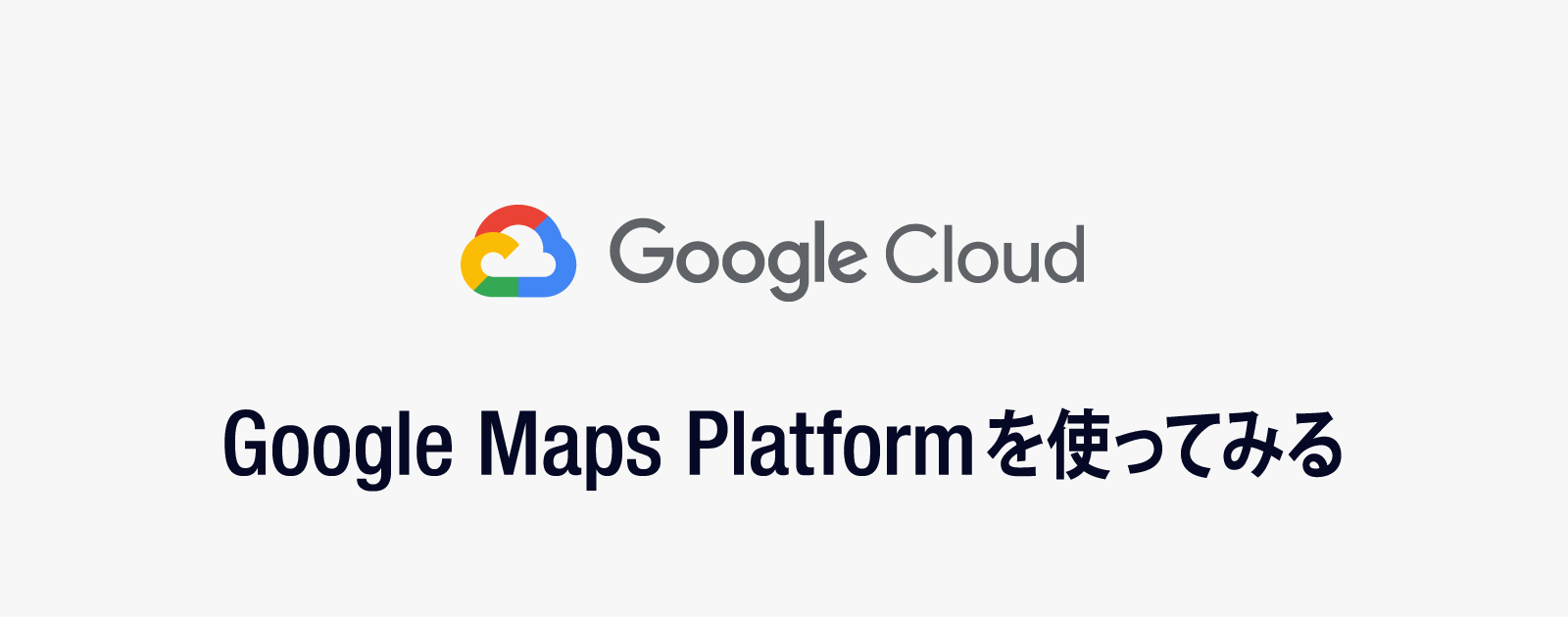 新しいGoogleマップ「Google Maps Platformの使い方」まとめ
新しいGoogleマップ「Google Maps Platformの使い方」まとめ 日本語で質問・回答できるプログラミング専門のQ&Aサイト
日本語で質問・回答できるプログラミング専門のQ&Aサイト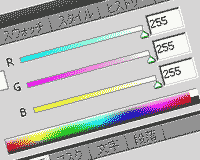 「人気ブログの作り方」もう色で悩まない!人気ブログから学ぶ色彩のテクニック
「人気ブログの作り方」もう色で悩まない!人気ブログから学ぶ色彩のテクニック 複雑で難しいWiki形式の表をExcelからコピー・ペーストする方法
複雑で難しいWiki形式の表をExcelからコピー・ペーストする方法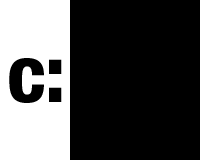 ゴミ箱を空にしてもCドライブの容量が一杯なときに時の試す3つのこと
ゴミ箱を空にしてもCドライブの容量が一杯なときに時の試す3つのこと