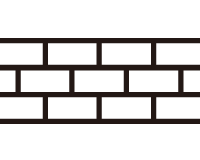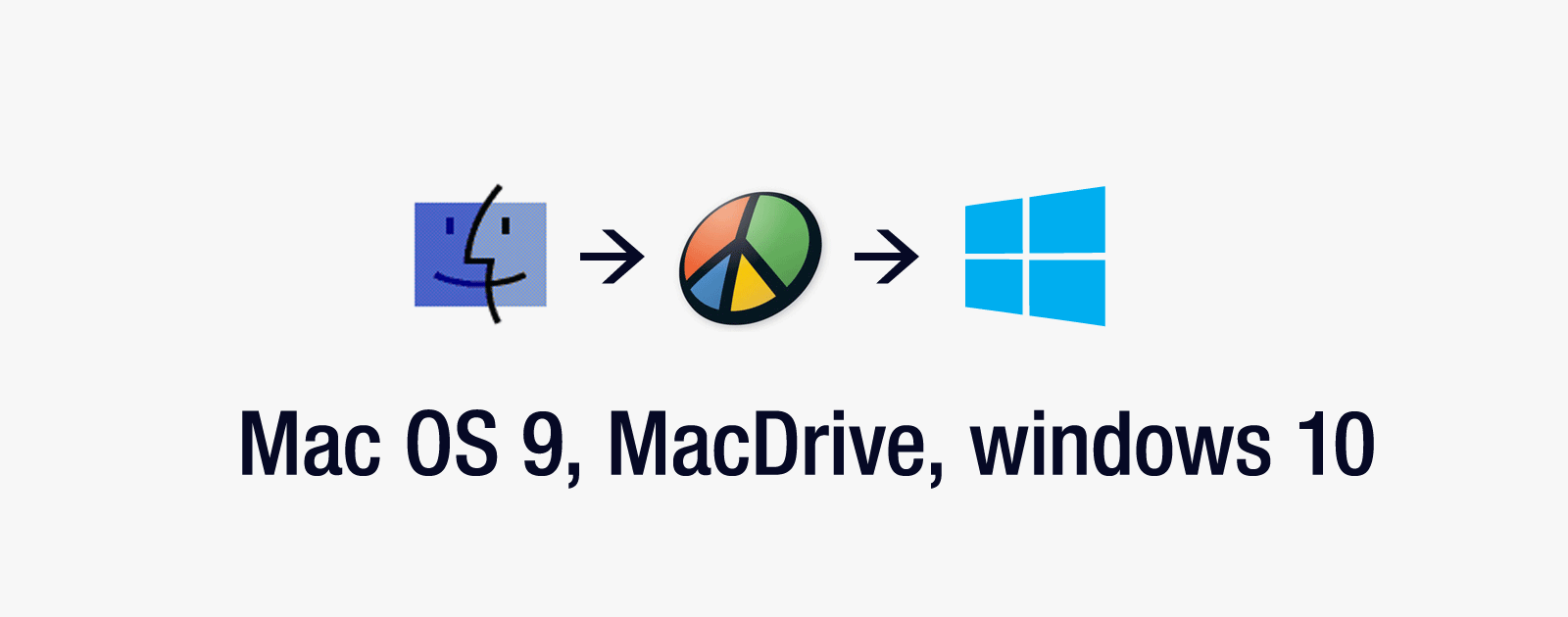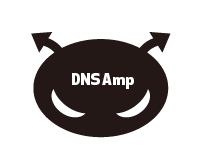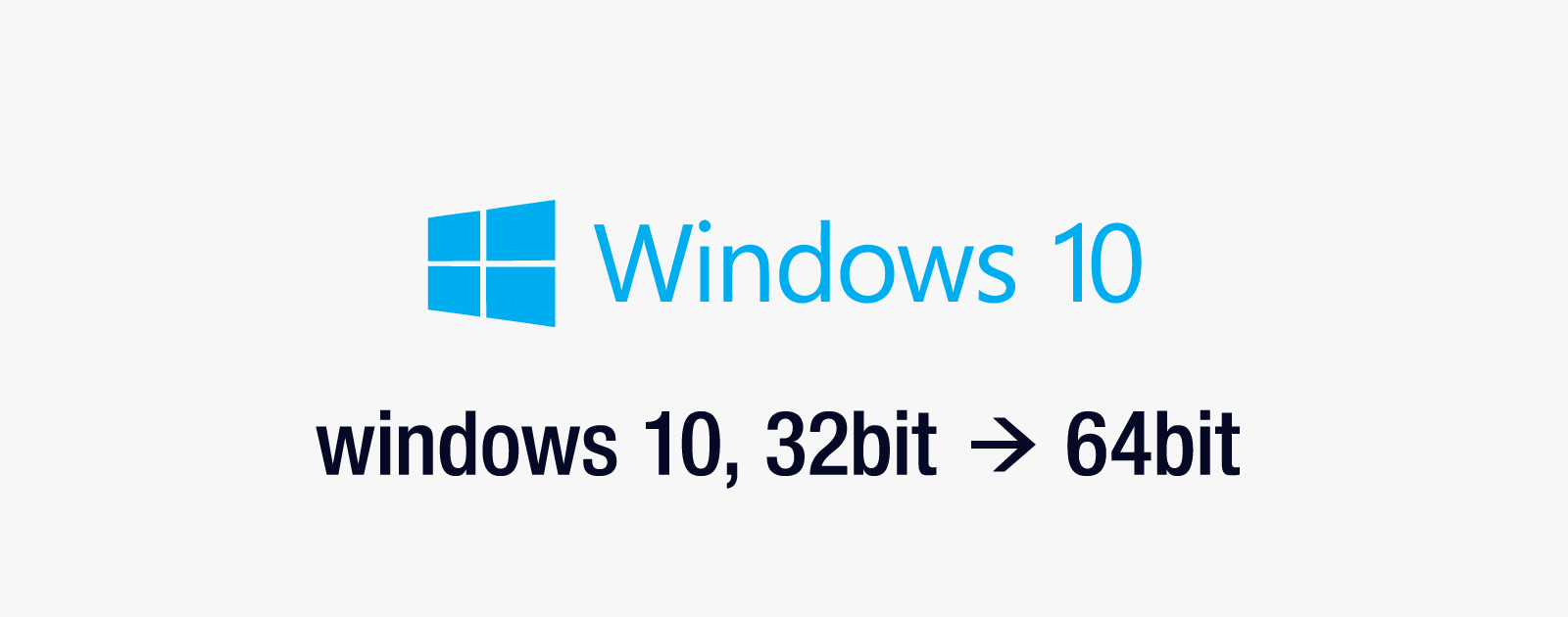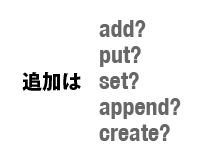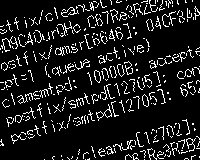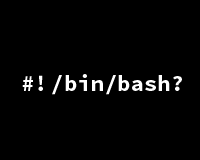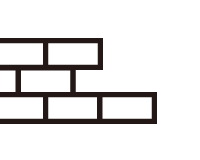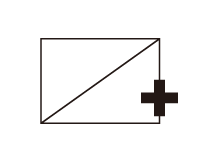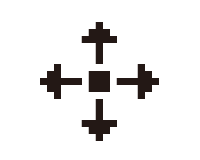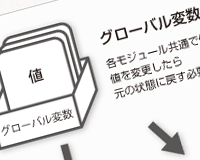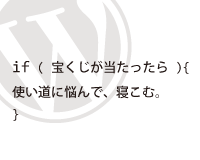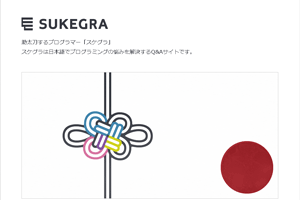元外務省官僚でクリスチャンの佐藤優氏が日蓮とルターという2人の宗教改革者について解説。
著者の結論を要約すれば、以下のようになります。
現在の日本は危機的状況。外はアメリカ、北朝鮮、中国と余談を許さない状況。内は政治家や官僚の腐敗が目に余る。
そのような時代にあって日蓮やルターに倣う高い倫理観を持つ改革者の出現が不可欠である。
という主張です。
日蓮とルター。生まれた年代も場所も違うものの、腐敗した聖職者や為政者に対して、敢然と立ち向かい、後に続く改革の流れを生み出したという点では共通点が多い。
日蓮もルターも既存の聖職者に対する間違いを指摘する際、法華経や聖書という文字を引いて論拠とした。カトリックや念仏にあるような死んだあとに幸せになるための信仰という彼岸的な視点から、現在の行いによって現世安穏を実現するという此岸(しがん)的視点を大切にしたという点も共通している。
また、権威主義と徹底的に戦うという姿勢から、国粋主義者や独裁者に利用されてきた点も合わせて指摘している。
日本で言う日蓮主義から国粋主義へと変遷した田中智学や、ルターの理論をユダヤ人虐殺を肯定するのに利用したアドルフ・ヒトラーなどです。
著者は日蓮とルターの両義性について指摘しています。立正安国論の結論を国を強化することで人が救われると解釈するのか、人を変えることで国を強化していくと解釈するのか。ルターについても対話を重視するタイプと、戦争などの暴力によって革命を起こすタイプに分かれている。しかしこれは2人の理論を剽窃したに過ぎません。
日蓮もルターもしっかりと学べば国粋主義やユダヤ人の排斥といった思想からは遠く離れたものです。ただし、そう信じさせたい人と、そう信じたい人々にとっては、変革者の高い意識や熱量を利用しやすいという指摘なのかもしれません。
これらの思想を現代でも体現して実行しているのは創価学会とプロテスタントだ。という構成になっています。
そして最後には堕落した政治家や官僚がいかに多いかを紹介。能力はあるが理想のないものや、能力も理想もないものが存在すると実例をもって紹介。これから国を良い方向に変えていくには能力だけでなく、高い倫理観をもって国を憂う人間こそ必要なのだ。宗教改革者の高い理想を持ち実践する人間が大切が求められる。
と、一応形としてはまとまっているのですが、連載という都合上、文字数を稼ぐために挟まれる蛇足が多い。主題を補足する形ならまだ我慢できるのですが、村上春樹の騎士団長殺しのあらすじを紹介したり、吉田茂が戦後処理について某国の大使館に出入りしていた、などといった小話を紹介して不要な混乱を生んでます。
さらには「作家は言いたいことを最初の本に書く。あとは蛇足だ」みたいなことも言い出します。それではこの本を読んでいる人に失礼な気もします。特に残念なのが蛇足が多い割に理論構築が脆弱で結論への誘導が強引です。立正安国論や聖書は自分で調べてみてくださいと言っているのですが、どうも著者の熱意が感じられません。全体が処女作の宣伝なのではないかと勘ぐりたくなります。
ということで、日蓮とルターについて全く知識がない人に向けて興味を抱かせることが目的の教養本といった印象です。
ここからは本の内容とは関係ない勝手な私見です。
著者は元官僚という立場で倫理観の欠如した同僚を告発しています。しかし、自分が有罪判決を受けて失職しなくても告発していたでしょうか。失職がなければ見て見ぬ振りをするつもりだったとしたら、著者の倫理観も特別高いとは言えないと思います。自らをプロテスタントと自称していますが、自身で紹介しているルターの「信仰即行動」を実践できていたのか疑問です。
背任と偽計業務妨害による有罪という結果も国策捜査として批判しているそうです。もし本当に国策捜査だったとしても長いものに巻かれていた著者にそうした捜査を批判する権利はあるでしょうか。
田中角栄などに代表されるように、大きな仕事を成し遂げた政治家で叩いて埃のでないものなど居ないでしょう。そんな連中と一蓮托生にならざるえない官僚も、気の毒といえば気の毒ですが…。国策のために超法規的な活動をさせられた人物が、国策捜査で逮捕される。時代に取り残された外交官ということなのかもしれません。
近年では官僚などの立場の高い人間の横暴を上級国民などといって非難する世論が噴出しています。政治家と連動する形なら多少の法律違反も許されるといった驕りはなかったか。
もちろん告発せずに黙っているよりはずっと良いですが。ある意味、罪を告白することで救わえる式の実践なのかもしれません。
ただし私は『国家の罠 外務省のラスプーチンと呼ばれて』を読んだことはないので、あくまで本書と、ネットの情報を見ただけの感想です。勘違いや間違っている点もあるかもしれません。