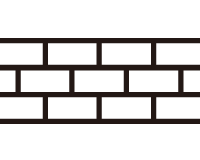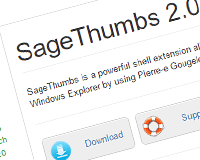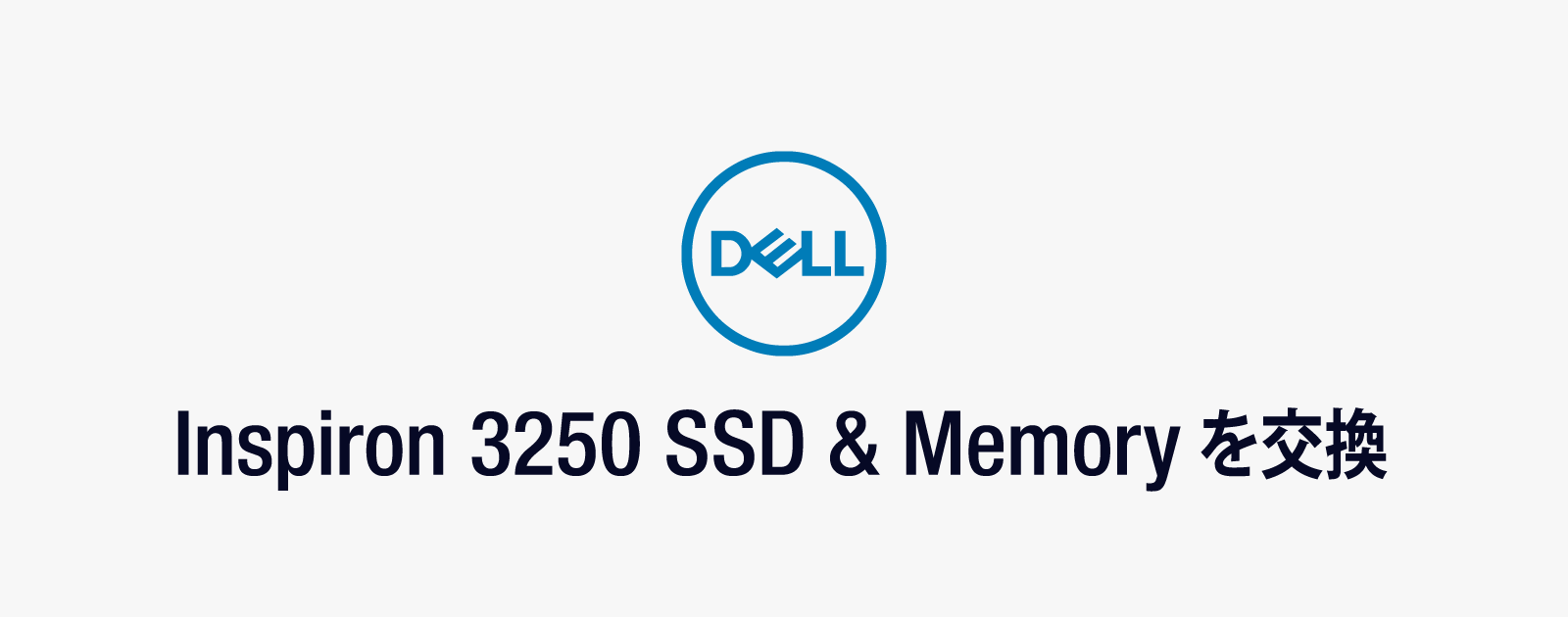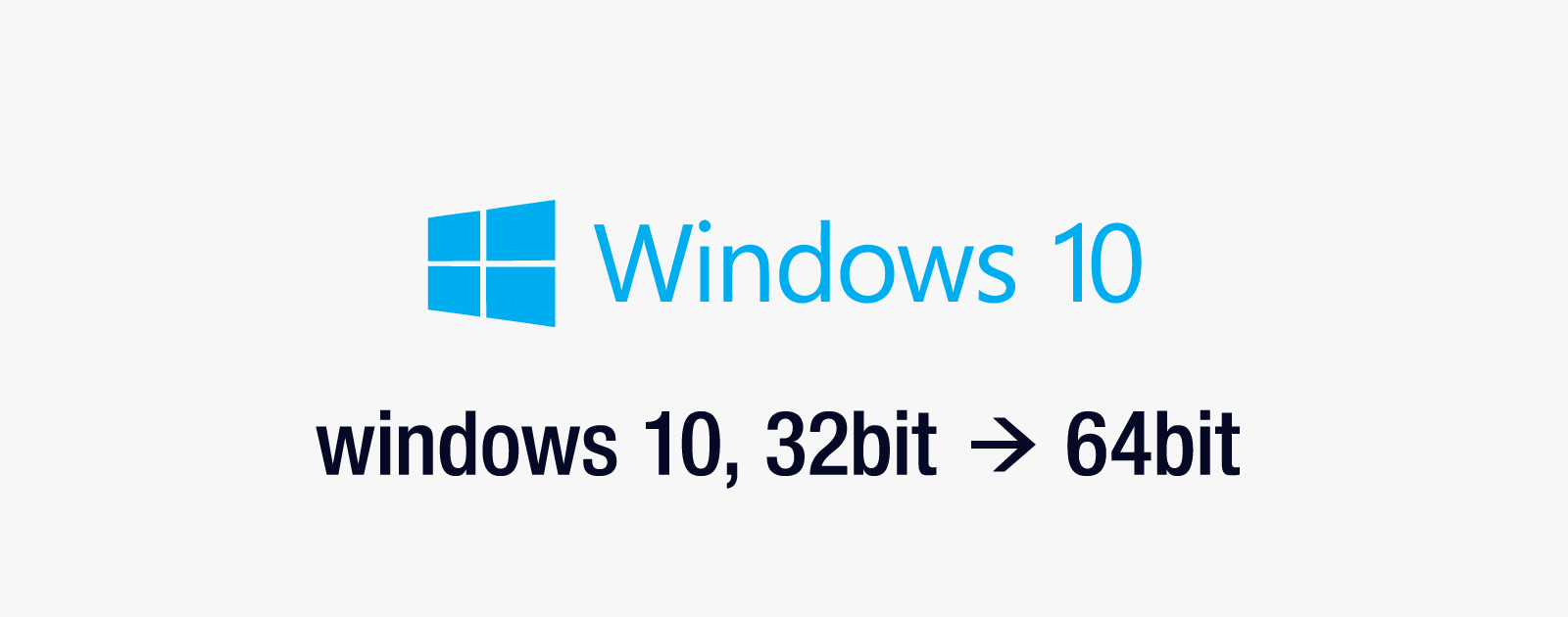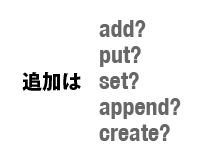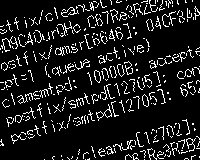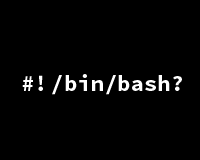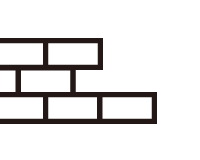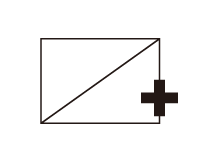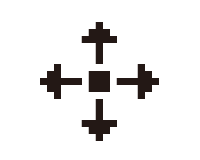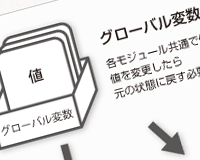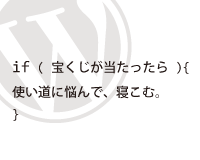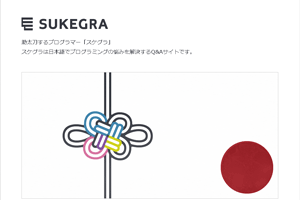オドルンダヨ。
有名な話しですが村上春樹は千駄ヶ谷でジャズバーを経営していました。
私の通った学校が千駄ヶ谷にあったため、有名なジャズバー跡地とは知らずに訪れたことがあります。
小説によく出てくる千駄ヶ谷や青山界隈の様子も手に取るようにわかります。
そんな縁もあり村上春樹に対しては勝手に「近所の有名なおっちゃん」的な親しみを持っています。
現代作家の本はあまり読まないのですが、珍しく手にとるのが村上春樹の作品です。
「ダンス・ダンス・ダンス」は僕という共通の主人公が登場する「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」「羊をめぐる冒険」の完結編。
私はこのうち「風の歌を聴け」しか読んだことがありません。
読書中に「僕」が共通していると気が付きませんでした。「いつも通り村上ワールドの主人公らしいや」程度の認識でした。
恥ずかしいことに解説を読んではじめて知りました。
ストーリーは独立しているため、本作だけ読んでも理解できるようになっています。(かつての友人「鼠」が骨として出てきますが、ストーリーの大筋とは関係ありません)
物語はとにかくメタファー、メタファー、メタファー。
俳優の五反田君は都会的で「成功」の対象として描かれる。同時に現代的な虚構の夢でもある。
対して主人公を惹きつける高級コールガールのキキは官能的であり享楽的。
才能に溢れ衝動的なアメ。才能が枯れ打算的な牧村拓。互いに対局にありながら、どちらも子供の感情を理解できない。
生の対象であるユミヨシさん。死の世界との橋渡しである羊男。
スバルとマセラッティ。
ドルフィンホテルを中心に、対極にある「メタファー」に振り回される「僕」。互いの引力で引かれ合い「僕」は振り子のように揺れ動く。一方ストーリーはDNAのらせん構造のように収束していく。
童話のような空想の世界かと思えば、急にドキュメンタリーのように写実的になる。
ドルフィンホテルとは何か。真相に近づきそうになるとさっと消えてしまう。謎は一向に解決しないが、魅力的な登場人物によって緩急が生まれ、物語に引き込まれる。
案内役は周囲の大人に振り回される13才の少女ユキ。多感な少女が時に音楽に逃避しながらも、「答え」を探して揺れ動き、ダンスを踊る「僕」と共鳴する。
まさに掴みどころのないストーリー。ひょっとすると読者にもダンスを求めているのかもしれません。
「オドルンダヨ。モノガタリノツヅクカギリ。」
印象的だったのは常に冷静な「僕」がユキに怒る場面。
「人の生命というものは君が考えているよりもずっと脆いものなんだ。だから人は悔いの残らないように人と接するべきなんだ。公平に、できることなら誠実に。そういう努力をしないで、人が死んで簡単に泣いて後悔したりするような人間を僕は好まない。個人的に」
「宇宙人、変な人」が誰とも馴染まず、多くの死を経験し、それでもダンスする「僕」の自戒の念なのかもしれません。
「経験」の数だけ、魂に重くのしかかります。

 ロリポップ!から「不正なアクセスを検知いたしました」というメールが届いた
ロリポップ!から「不正なアクセスを検知いたしました」というメールが届いた WordPress公式テーマTwenty Tenを子テーマでレスポンシブWebデザインに変更
WordPress公式テーマTwenty Tenを子テーマでレスポンシブWebデザインに変更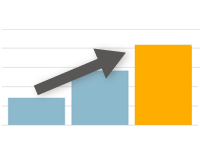 手間をかけずにWordPressのスパムを1/25に減らす対策
手間をかけずにWordPressのスパムを1/25に減らす対策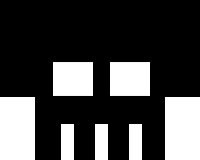 ロリポップ!で起きている大規模な改ざんからWordPressサイトを守る方法
ロリポップ!で起きている大規模な改ざんからWordPressサイトを守る方法 同一IPによる大量のスパムコメントを.htaccessでアクセス規制する方法
同一IPによる大量のスパムコメントを.htaccessでアクセス規制する方法 知らないうちにロリポップ!にバックドアが仕掛けられていた!
知らないうちにロリポップ!にバックドアが仕掛けられていた! WordPressの予約投稿が失敗した時に試す4つの解決策
WordPressの予約投稿が失敗した時に試す4つの解決策